昨今、Web3.0というキーワードが急速に注目を集めています。
次世代ウェブとしてWeb3.0という言葉が使われ始めたのはしばらく前からだが、その定義は人によってさまざまだった。しかしここ2〜3年は、「ブロックチェーン技術を基盤とする分散型の取引機能を伴う次世代のウェブ」という定義が定着してきました。
2021年からはブロックチェーン業界だけでなく、特に米国のテクノロジー業界において、「Web3.0は90年代のインターネット革命を超える規模の新たな革命である」という認識の下、国家戦略として政府が真剣に取り組むべき対象であるという論調が強まってきています。
今回は、Web3.0とは何か、WEB1.0、WEB2.0と共に分かりやすく解説します。
・WEB3.0とは何か
・WEB3.0は社会に何をもたらすか。
・WEB3.0に関連する暗号資産(仮想通貨)
WEB3.0とは何か

Web3.0とは、ブロックチェーン技術を活用した分散型ウェブのことです。

FacebookやGoogle、Twitterなどの巨大なテック企業を排除して、
情報へのアクセスとデータ利用を民主化する様々な取り組みの総称とも言えます。
この世界では、巨大企業ではなくユーザー自身がデータを保持して(分散化)、ネットワーク上のデータの正しさがシステムによって検証され(透明性 / 検証可能性)、ネットワークやデータの一部を所有することで(所有権)、収益化することもできます(経済的インセンティブ)。
具体的に言えば、ユーザーは自身の個人情報をテック企業に渡さないまま、検索やソーシャルネットワーキング、データ保存、金融などの各種サービスを利用することができます。
また、ブロックチェーン技術を利用して発行された暗号資産(仮想通貨)である「トークン」を介して、運営に参加したり報酬を得ることも可能。
Web3.0では、NFTやDeFi、DAOのような事例もあり、それらはブロックチェーン技術によって支えられています。つまり、Web3.0 とは具体的なサービスやビジネスモデル、技術を指すのではなく、より広範な理念や概念であると言えます。
WEB3.0はWEB1.0、2.0を知ることで理解が深まります。次はそれらを解説していきます。
WEB1.0とは
一般的に、Web1.0 の時期はインターネットが普及しはじめた1990年代半ばから、Web2.0 が生まれる2000年代半ばまでを指します。
この時代は、HTMLでつくられた静的なウェブサイトが中心で、ユーザーもそのウェブサイトを閲覧するだけに留まり、何かを買ったり、コンテンツを投稿したり、あるいは相互にアクションしあうことは殆どありませんでした。
つまり閲覧のみであり、静的な世界だと言えます。
WEB2.0とは
これに対して Web2.0 は、すでに見てきたようにGoogle、Facebook、Amazon、Appleなどのテック企業に代表される世界です。
静的なウェブサイトではなく、情報がデーターベースに格納され、コンテンツが動的に生成され、ユーザーが相互にアクションをおこない(たとえばフォローやいいねなど)、巨大プラットフォーマーたちのサービス上で消費者は多くの時間を過ごしています。
つまり読み書きができて、相互作用がある世界です。
この流れの中で、大規模なネットワークを生み出し、広告などのビジネスモデルを通じて商業的成功を収めるプレイヤーが生まれてきました。
それが、ビッグテックと呼ばれる企業です。
彼らの誕生と急成長によって、検索やメール、データの保存や共有、友人との会話、動画の閲覧などの各種サービスは多くが無料で提供され、モノやサービスの購入は格段に便利になりました。
その結果、2010年代後半からのインターネットは、Google や Facebook、Amazon、Appleなどのサービスで完結するようになり、ビッグテックの力は強大になっていきました。
しかし、このビッグテックによる寡占とも言える状況は、大きな利便性を生みつつも弊害ももたらしました。
WEB2.0の弊害
1.データの独占
2017年、The Economist誌がおこなった「世界で最も価値がある資源は、石油ではなくデータだ」という有名な指摘にあるように、こうした企業は消費者のありとあらゆるデータを集めることで、膨大な利益を手に入れました。
こうした問題は、単なる独占的な地位による不当な利益という論点だけでなく、プライバシーの権利や表現の自由など基本的人権への侵害という論点にまで広がっています。
加えて、データの独占やアルゴリズムへの利用は、ヘイトスピーチやフェイクニュースなど、社会の健全性や民主主義のガバナンスを揺るがしていると言われています。
2016年の米国大統領選挙をきっかけとして「社会的分断」が問題視されるようになり、ビッグテックがそれを加速させているという論調が強まっていきました。
2.透明性の欠如
収集されたデータがどのように使われているか?プラットフォーム上でどのようなアルゴリズムが動いているか?危害を生み出す可能性のあるコンテンツ(たとえば)をどのようにモデレート(管理)しているのか?などの説明責任が十分に果たされていない、という批判があります。
こうした問題意識から欧州委員会は、2020年にデジタルサービスアクト(DSA)を公表して、「オンライン上のコンテンツに関連する被害と、その結果についての透明性を高める」ことを目指しています。米国でも、政府の監視機関を設けるべきだという論調や科学的根拠にもとづく独立した監視委員会を求める声が高まっています。
特に今年9月、Facebook の傘下にある Instagram が、10代女性のメンタルヘルスにとって自社サービスの悪影響を知りながらも、十分な対策を講じていないことが明らかになり、規制を求める声は拡大しています。Facebook はすでに、表現の自由に関連した独立委員会を設置しています。
3.所有権の不在
ビッグ・テックによるデータの吸い上げによって、消費者側に所有権がないことも問題視されています。
これは、ビッグ・テックが個人情報や様々なデータの所有権を持ち、本人よりもその欲求とニーズを理解している問題に限らず、ゲームアイテムや映像、画像など、クリエイターによって生み出されたコンテンツが、ビッグ・テックによって所有されている問題を指しています。
WEB3.0は社会に何をもたらすか

WEB1.0から2.0へ発展し、私たちの生活の利便性は劇的に向上しました。
一方で前述した弊害がもたらされたのも事実です。
WEB3.0はそれらの弊害をなくすことが期待されています。
それらを解説していきます。
1.分散化
Web3 の世界では、ビッグテックに独占された個人情報やデータが分散化によって市民の手に取り戻されることが挙げられる。たとえば、NFTのマーケットプレイスである OpenSea などを利用する際、MetaMask(メタマスク)と呼ばれる仮想通貨ウォレットを通じてログインする。これは従来の Facebook や Google によるログインとは異なり、自身のアイデンティティを自ら所有する仕組みだ。
散化の利点は、サーバーがダウンしたり障害が発生してもサービスが利用し続けられることや、ハッキングのリスクを減らせること、De-Platforming や no-platforming を回避できることが挙げられます。ま
2.透明性
従来であれば、Facebook や Google などのビッグ・テックや政府などを信頼することで、人々は貨幣制度や法制度への参加、個人情報の提供などをおこなってきた。しかし Web2.0 の弊害で述べたように、その透明性と説明責任に疑念が生まれたとしても、現実的にその制度から抜け出すことは不可能でした。
これに対してブロックチェーンは、その技術的特性によってデータやネットワーク自体の正しさを検証していき、それは透明性によって基礎づけられています。つまり、透明性によって誰もがデータを検証することができる。
3.所有権
単一の中央管理者が存在していないため、ユーザーが自身のデータ所有権を掌握でき、データがユーザーの許可なく利用されることはありません。この前提の下、ユーザーが許可した場合のみ、そのデータが共有されるため、現在のように、ユーザーの知らないところでデータが売買されるなどの状況が改善されます。
WEB3.0に関連する暗号資産(仮想通貨)

WEB3.0の概要が分かったところで、次はこの変化に対応し、資産を形成していく為の暗号資産(仮想通貨)をプロジェクトと一緒に紹介致します。
それぞれのプロジェクトを理解し、投資の判断をしてみて下さい。
プロジェクト:Brave — Web3.0ブラウザ
Brave(ブレイブ)とは、プライバシーに配慮した分散型広告システムを搭載している、Web3.0系のブラウザです。
従来の広告モデルでは、広告主およびユーザーの間でリアルタイムの入札が行われることにより、ユーザーへ広告が表示されていました。
このモデルでは、広告主およびパブリッシャー(広告を表示するプラットフォーム運営者)の利害が一致し、収益が最適化されている一方、ユーザーの同意なしに広告が表示されています。
そのため、ユーザーの許可なしで広告用の画像および動画がダウンロードされ、デバイスの負担が増加しているだけでなく、広告主を初めとして、ユーザーの管理が及ばないところで、ユーザーのデータが共有されています。
この状況を問題視しているBraveのブラウザ上では、従来の広告モデルではなく、プライバシー保護に特化した、独自の広告モデルが採用されています。Braveの広告モデルでは、ユーザーのデバイス上で、広告のマッチングが行われるため、ユーザーの情報がローカルデバイスから流出することはありません。
また、広告ブロック機能がデフォルトで搭載されているため、ユーザーの許可なしに広告が表示されることもありません。広告が表示される場合は、ユーザーの合意の下、ユーザーにとって負担にならないサイズの素材で表示されます。
Braveでは、この新たな広告モデルを稼働する経済的インセンティブとして、BATトークンを導入しています。
関連する仮想通貨:ベーシック・アテンション・トークン(BAT)
通貨(トークン名) ベーシック・アテンション・トークン
ティッカーシンボル・単位 BAT
現在の価格(2022年1月時点)約98円
時価総額(2022年1月時点)約1,430億円
公式サイト https://basicattentiontoken.org/ja/team/
BAT(Basic Attention Token/ベーシックアテンショントークン)とは、現在のデジタル広告業界の課題を解決するために開発されたトークンです。BATは、プライバシーに焦点を当てたブラウザ、Braveのネイティブトークンであり、Braveの新たな広告モデルにより、デジタル広告業界が大きく変容する可能性があると多くの注目を集めています。国内の仮想通貨取引所でも、BATを取り扱う取引所が増えてきています。
プロジェクト:IPFS・FilecoinーWeb3.0
ファイルストレージオープンソース技術開発および研究機関「Protocol Labs(プロトコルラボ)」は、単一障害点のない分散的な方法でファイルの保管を可能にするシステム、IPFS(InterPlanetary File System)およびFilecoin(FIL)の開発を行っています。
これらにより、従来GoogleクラウドやAWS(Amazon Web Services/アマゾンウェブサービス)が提供してきたサービスを、ピアツーピアで行うことできます。
最近では、後述のBraveが、IPFSをネイティブにサポートすることを発表し、話題となりました。
IPFSとは、現在インターネットで一般的に利用されている「HTTP」プロトコルに代わる、ピアツーピアのプロトコルです。HTTPプロトコルは、サーバーに保管されているファイルの中から、クライアントが取得したいファイルの場所を指定する「ロケーション指向型」プロトコルであり、クライアントの要求にサーバーが応えるような形で機能しています。
このような仕組みから、サーバーに権力が集中する、中央集権的構造になっています。
一方でIPSFは、ハッシュ値で表されたファイルのコンテンツを指定することによりファイルを取得する「コンテンツ指向型」プロトコルであるため、一つのサーバーに依存せずに、複数のネットワーク参加者が同じハッシュ値(=コンテンツ)を所有できます。これにより、分散的なファイル保管が可能になります。
関連する仮想通貨:ファイルコイン(FIL)
通貨(トークン名) ファイルコイン
ティッカーシンボル・単位 FIL
現在の価格(2022年1月時点)約2,250円
時価総額(2022年1月時点)約3,495億円
公式サイト https://filecoin.io/
Filecoinとは、ファイル保管を可能にしているピアツーピアのネットワークであり、IPFSに欠如している経済的インセンティブを補完しています。IPFSでは分散的な方法でファイル保管が可能ですが、他のユーザーのファイルを保管しておくためのインセンティブが内在していません。
そこで、Filecoinの仕組みをIPFS上に構築し、ファイル保管スペースを他のユーザーに貸し出したユーザーに対して、Filecoinで報酬を与えることにより、一種のファイル保管スペース市場、および経済的インセンティブが創出されています。
プロジェクト:Web3 FoundationーWeb3.0促進組織
Web3 Foundationとは、分散型ウェブ用アプリケーション開発を促進する組織であり、イーサリアムの共同創設者兼元CTOのGavin Wood博士を中心に設立されました。
Web3 Foundationは、「企業ではなくユーザーがデータ管理」、「安全かつグローバルなデジタルトランザクション」「分散型の情報および価値交換」を信条に運営されています。
Web3.0発展を目的として、Web3 Foundationは、分散型ソフトウェアプロトコル分野のプロジェクトおよびリサーチ機関を対象に、助成金プログラムを実施しています。これまでに50以上の国で、200を超える多種多様なプロジェクトが助成金を受け取ってきました。
関連する仮想通貨:ポルカドット(DOT)
通貨(トークン名) ポルカドット
ティッカーシンボル・単位 DOT
現在の価格(2022年1月時点)約2,035円
時価総額(2022年1月時点)約2.31兆円
公式サイト https://polkadot.network/ja/
Polkadot(ポルカドット)とは、Web3 Foundationが主導で開発を行う、相互運用性強化に特化したネットワークです。ブロックチェーンを初めとした分散型台帳技術の発展により、Web3.0の実現可能性が高まっている一方で、現在のブロックチェーン技術では、特に異なるチェーン同士の相互運用性、およびスケーラビリティ(拡張性)に限界があります。
Polkadotは、ネットワークの中核を担う「リレーチェーン」、およびリレーチェーンに並行に接続する「パラチェーン」という独自のネットワーク構造を有することにより、このようなボトルネック解消に取り組んでいます。
まとめ
WEB3.0とは何か。WEB2.0時代にもたらされた弊害をなくすことが期待され、アメリカでは国家戦略レベルで取り組んでいます。
この変革を理解し、投資機会にすることが私たちの資産形成につながります。
本記事があなたの投資判断の一助になれば幸いです。






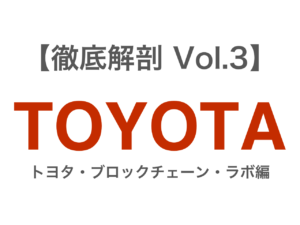


コメント